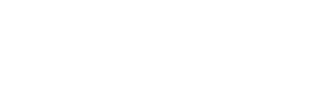相続の際、「生前贈与を受けた人は遺産が少なくなるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、相続人の中に生前贈与を受けた人がいると、その人が他の相続人と同じ割合で遺産をもらうと不公平になる場合があります。そのため、法律では「特別受益」というルールを設け、相続財産の計算方法を調整しています。
本コラムでは、生前贈与が相続にどう影響するのか、特別受益とは何か、具体的な計算方法についてわかりやすく解説します。
このページの目次
1. 特別受益とは?
「特別受益」とは、被相続人(亡くなった方)から生前に特別な贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与分を考慮して相続財産を調整する制度です。
たとえば、被相続人が生前に子どもAに600万円を贈与していた場合、相続財産の分配に影響が出る可能性があります。
具体例
- 相続財産:3000万円
- 相続人:子どもA、B、C(各1/3ずつ)
- Aは生前に600万円を贈与されていた
この場合、相続財産に600万円を加えた「3600万円」を基準に相続分を計算します。
- 各相続人の基本相続分:3600万円 × 1/3 = 1200万円
- Aの受け取る最終額:1200万円 - 600万円 = 600万円
- BとCの受け取る額:各1200万円
このように、生前贈与を考慮することで、相続人間の公平性が保たれます。
2. 「持戻し免除」のルールとは?
被相続人が「生前贈与分は相続財産に含めない」と意思表示をしていた場合、「持戻し免除」が適用されます。これにより、生前贈与を受けた相続人が不利にならないケースもあります。
この意思表示は、
- 明示(書面や口頭で明確に伝える)
- 黙示(状況から判断できる)
どちらでも可能です。また、遺贈(遺言による財産の譲渡)の場合は、遺言書に記載が必要です。
3. 特別受益の期間制限
特別受益の持戻しには、期間制限があることにも注意しましょう。
重要なポイント
- 遺産分割の請求は、相続開始から10年以内に行う必要がある
- 生前贈与の持戻し対象は、相続開始前10年以内のものに限定される(遺留分を算定する場合)
この期間を過ぎると、特別受益を主張できなくなる可能性があります。遺産分割が長引かないよう、早めに対応することが大切です。
4. まとめ
生前贈与があると、相続財産の計算方法が変わることがあります。特別受益や持ち戻し免除のルールを理解し、相続トラブルを防ぎましょう。
「自分のケースではどうなるの?」と不安な方は、専門家に相談するのが一番です。
結の杜総合法律事務所では、相続に関するご相談を丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。