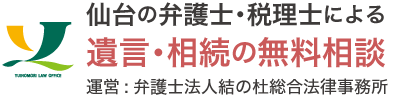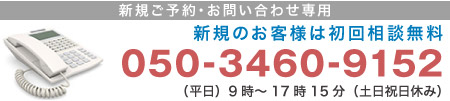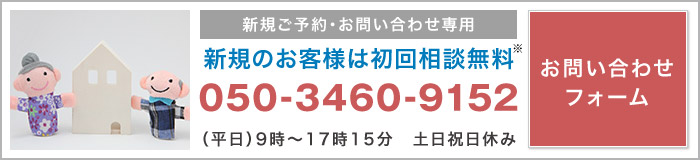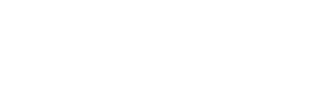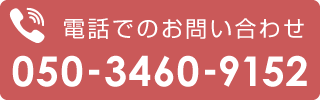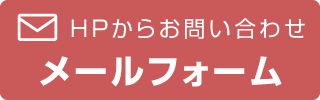このページの目次
1 はじめに
「父が亡くなり、葬儀費用がすぐに必要ですが、遺産分割の話し合いはまだできていません。父名義の預金を引き出して支払うことは可能でしょうか。」
このようなご相談は非常に多く寄せられます。実際、相続開始後は預金口座が凍結されるため、自由に払戻しを受けられないケースが多くあります。では、遺産分割前でも預金の払戻しはできるのか、最新の法律と実務をもとに解説します。
2 相続が開始すると口座は凍結される
被相続人が死亡すると、銀行などの金融機関はその事実を確認した時点で預金口座を凍結します。これにより、預金の引き出しや口座振替は停止され、原則として相続人全員の同意や遺産分割協議が整うまで払戻しはできません。
3 過去の取り扱いと最高裁の判断
かつては、預金を「可分債権」と考え、一部の相続人が自分の法定相続分を単独で引き出せるとする見解もありました。しかし実務は統一されず、銀行ごとに対応が異なっていました。
この点について、平成28年12月19日最高裁決定は「預貯金は遺産分割の対象であり、相続開始と同時に分割されるものではない」と判示しました。これにより、遺産分割前に相続人が単独で預金を引き出すことは原則できなくなりました。
4 法律改正による新しい払戻制度
その後の法改正(令和元年7月1日施行)により、相続人が葬儀費用や生活費に充てるために一定額の払戻しを受けられる制度が導入されました。
-
民法909条の2に基づく払戻し
相続人は、各金融機関ごとに「150万円」を上限として、遺産分割前でも単独で払戻し請求が可能です。 -
家庭裁判所による保全処分(仮分割の仮処分)
上限額を超える払戻しが必要な場合は、家庭裁判所に申立てを行うことで、葬儀費用や相続人の生活費等に充てるための預金払戻しが認められる場合があります。
5 実際に引き出せる金額の目安
例えば、被相続人がA銀行に普通預金600万円・定期預金900万円、B銀行に普通預金780万円を残していた場合、法定相続分2分の1の相続人は以下の金額まで払戻しが可能です。
-
A銀行:上限150万円
-
B銀行:130万円(780万円×1/3×1/2)
つまり合計280万円を遺産分割前に引き出せる計算になります。
6 必要書類と手続き
払戻しを受けるためには、各銀行の「相続届(一部払戻用)」を提出します。併せて、以下の書類が必要となります。
-
被相続人の通帳・証書・キャッシュカード
-
被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等
-
相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図
-
請求者相続人の印鑑登録証明書
銀行や状況によっては追加書類を求められる場合があります。
7 弁護士に相談すべきケース
-
葬儀費用や当面の生活費に充てるため、できるだけ早く預金を引き出したい
-
相続人間で意見が合わず、手続きが進まない
-
預金以外に不動産・株式なども含まれており、遺産分割が複雑になりそう
このような場合は、弁護士にご相談いただくことで、最適な手続きの選択肢や金融機関との交渉方法を明確にすることができます。
8 まとめ
-
相続開始後、被相続人名義の口座は凍結される。
-
遺産分割前でも、法改正により 各金融機関150万円までの払戻し が可能。
-
上限額を超える場合は、家庭裁判所の「保全処分」を利用できる。
-
手続きには戸籍謄本や相続届など複数の書類が必要。
遺産分割や預金払戻しの問題は、法律と税務の両面の知識が不可欠です。
9 結の杜総合法律事務所にご相談ください
当事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設しており、東北では唯一の「弁護士+税理士」のワンストップ体制を整えています。
相続手続き・遺産分割・相続税申告まで一貫して対応可能です。
-
初回相談無料
-
手続きの流れや費用を明確にご説明
-
無理な勧誘は一切なし
「葬儀費用を支払うためにすぐにお金が必要」「口座凍結で困っている」といった方は、まずはお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。