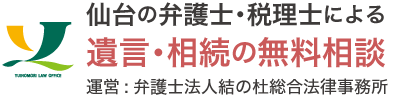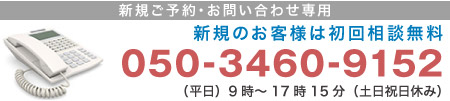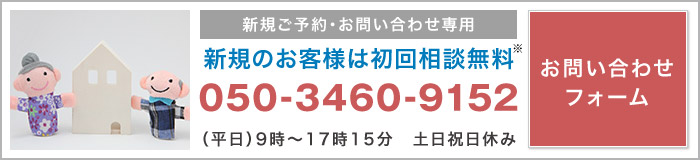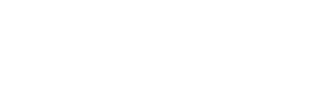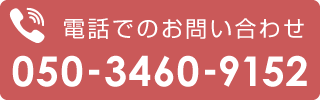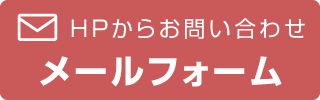このページの目次
1 はじめに
「親が自筆証書遺言を残していたが、押印がなく無効だといわれた。記載されている内容通りに財産を取得できないのか?」
このようなご相談を受けることがあります。
結論から言うと、押印を欠いた遺言は原則無効です。しかし、場合によっては『死因贈与契約』として有効に扱える可能性があります。
本記事では、死因贈与とは何か、遺言との違い、税金上の注意点について、弁護士かつ税理士がわかりやすく解説します。
2 死因贈与と遺言の関係(法的性質)
民法554条では「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与」=死因贈与と規定されています。
遺贈と似ていますが、厳密には以下の点が異なります。
-
死因贈与は「生前贈与の一種」であり、贈与者の死亡を始期とする期限付贈与と考えられる。
-
遺言は死亡まで効力を発しませんが、死因贈与は契約成立時点で受贈者に「期待権」が生じます。
3 死因贈与と遺言の違い(4つの視点)
(1) 撤回の可否
-
遺言は自由に撤回可能。
-
死因贈与は契約であるため、原則撤回できません。判例(最判昭58・1・24)でも同様の立場がとられています。
(2) 贈与財産の処分
-
遺言:死亡まで効力がない → その間の処分は「撤回」とみなされる。
-
死因贈与:契約成立済み → 抵触する処分は「債務不履行」として扱われる。
(3) 方式
-
遺言:自筆証書、公正証書など厳格な方式が必要。
-
死因贈与:口頭でも契約可能。契約書も全文自筆である必要なし。
(4) 効力と承継
-
死因贈与契約成立時点で受贈者に期待権が発生。
-
贈与者死亡後、受贈者が既に亡くなっていれば、その相続人が権利を引き継げる。
4 死因贈与と税金(相続税・不動産取得税・登録免許税の違い)
(1) 相続税
-
共通点:遺贈も死因贈与も、相続税の課税対象になります。
(2) 不動産取得税
-
遺贈による取得:非課税。
-
死因贈与による取得:課税対象。仙台高裁判例(平成2年12月25日)でも確認されています。
(3) 登録免許税
-
相続人への遺贈:相続と同じ税率(不動産価額の1,000分の4)。
-
死因贈与:相続人であっても高い税率(不動産価額の1,000分の20)が課される。
5 無効な遺言書と死因贈与契約
押印がない、印字が多いなど形式を欠いた遺言書は無効です。
しかし、そこに署名があり、さらに受贈者への口頭申入れと承諾があれば、死因贈与契約が成立したと認められる余地があります。
実務では「遺言が無効=全て諦める」ではなく、死因贈与の可能性を検討することが重要です。
6 まとめ
-
死因贈与は「契約」であり、遺言と異なり撤回が制限され、税金面でも扱いが変わる。
-
相続税は共通だが、不動産取得税や登録免許税では大きな差がある。
-
無効な遺言があっても、死因贈与契約として認められる可能性がある。
7 相続・死因贈与のご相談は結の杜総合法律事務所へ
当事務所は、弁護士法人と税理士法人を併設運営している東北唯一の法律事務所です。
相続・遺言・死因贈与・相続税申告など、法律と税務の両面からワンストップでご相談いただけます。
-
遺言書の有効性や死因贈与契約の成立可能性を確認したい
-
不動産の相続や税金(相続税・不動産取得税・登録免許税)が心配
-
仙台・宮城で相続手続に強い専門家を探している
このようなお悩みをお持ちの方は、まずはお気軽にご相談ください。
初回相談では、弁護士・税理士が直接わかりやすくご説明し、ご納得いただいた上でサポートいたします。
👉 [お問い合わせはこちら]
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。