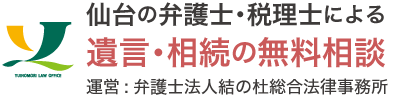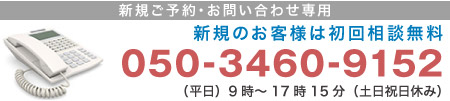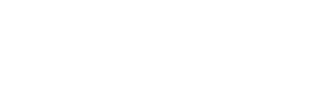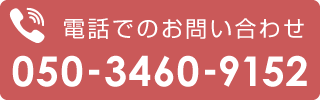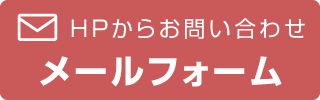Author Archive
『令和8年3月の土曜相談日』のお知らせ
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月2回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料】。
令和8年3月の相談日は次の通りです。
① 3月 7日(土)(担当弁護士:髙橋)
② 3月14日(土)(担当弁護士:三塚)
お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。
相談場所は、原則として五橋本店となります。
(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)
また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。
皆様のご予約をお待ちしております。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
コラム「【仙台の弁護士が解説】遺言無効の訴えとは?手続・判例・遺留分との関係をわかりやすく解説」
「この遺言書は本当に有効なのか?」
「認知症だった親の遺言を争うことはできるのか?」
「公正証書遺言でも無効になることがあるのか?」
相続の現場では、遺言の有効性をめぐる争い(遺言無効確認訴訟)が少なくありません。
本記事では、
-
遺言が無効になるケース
-
遺言無効確認の訴えの手続
-
被告の選び方
-
立証責任
-
遺留分侵害額請求との関係
について、判例を踏まえて解説します。
仙台・宮城で相続問題にお悩みの方は、ぜひ参考になさってください。
1 遺言が無効になる場合とは?
(1)遺言は原則として尊重される
遺言は、遺言者の最終意思を尊重する制度です。
有効な遺言があれば、原則としてその内容どおりに遺産は承継されます。
しかし、一定の場合には遺言そのものが無効となります。
(2)方式違反による無効
遺言は「要式行為」です。
法律(民法960条以下)で定められた方式を守らなければなりません。
例えば、自筆証書遺言の場合、
-
全文自書
-
日付の自書
-
氏名の自書
-
押印
が必要です。
これらを欠く場合、遺言は無効となります。
(3)遺言能力の欠如(民法963条)
遺言作成時に遺言能力(事理弁識能力)がなければ、遺言は無効です。
典型例:
-
重度の認知症
-
意識障害
-
精神疾患による判断能力の欠如
もっとも、「認知症=直ちに無効」ではありません。
診断書、カルテ、介護記録、作成経緯などを総合的に判断します。
実務上、最も争いが多いのがこの「遺言能力」の問題です。
(4)その他の無効原因
-
公序良俗違反
-
詐欺・強迫
-
証人の欠格事由
-
受遺者の先死亡
-
民法総則による無効・取消事由
2 遺言無効確認の訴えとは?
遺言の有効性に争いがあり、話し合いで解決できない場合、
最終的には遺言無効確認の訴え(民事訴訟)を提起します。
(1)まずは調停から
いきなり訴訟ではなく、
-
遺言無効確認調停
-
遺産分割調停
から開始することもあります。
しかし、当事者の主張が鋭く対立している場合は、訴訟による解決が必要になります。
(2)誰が原告になれるか?
遺言の無効を主張する者が原告になります。
「すでに生前贈与を受けており、法定相続分がない場合でも訴えられるのか?」
この点について、最高裁(最判昭56年9月11日)は、確認の利益は遺言内容で判断すれば足りるとして、原告適格を認めています。
したがって、生前贈与を受けていても原告になることは可能です。
(3)誰を被告にするべきか?
実務上重要なポイントです。
原則:
-
遺言により利益を受ける受遺者
が被告になります。
最高裁(最判昭56年9月11日)は、単なる相続分指定などの場合は固有必要的共同訴訟にはならない(共同相続人全員を被告とする必要はない)と判示しています。
もっとも、遺産確認を求める場合(最判平成元年3月28日)は、共同相続人全員を当事者とすべきとされています。
遺言内容により判断が分かれるため、専門的検討が不可欠です。
(4)遺言執行者を被告にできるか?
最高裁(最判昭31年9月18日)は、遺言執行者を被告として無効を争うことを認めています。
ただし、既に所有権移転登記がなされている場合は、受遺者を被告とすべきとされています(最判昭51年7月19日)。
(5)立証責任の分配
非常に重要なポイントです。
■ 遺言の方式遵守
→ 遺言が有効と主張する側が立証責任(最判昭62年10月8日)
■ 遺言能力の欠如など
→ 無効を主張する原告側が立証責任
遺言能力の立証では、
-
医療記録
-
介護記録
-
証人尋問
-
作成経緯
などを総合的に主張立証します。
3 遺言無効と遺留分侵害額請求の関係【最重要ポイント】
(1)必ず遺留分請求を並行して検討すべき理由
遺言無効確認訴訟は、長期化することが少なくありません。
しかし、遺留分侵害額請求には、「相続開始および侵害を知った時から1年」という短い消滅時効(民法1048条)があります。
訴訟中に時効が完成してしまうリスクがあるのです。
したがって、
✔ 遺言無効を争う
✔ 同時に遺留分侵害額請求の意思表示を行う
ことが極めて重要です。
実務では、内容証明郵便で通知するのが安全です。
(2)同一訴訟で予備的請求を入れるべきか?
理論上は可能ですが、実務上は推奨されません。
理由:
-
争点が複雑化する
-
訴訟が長期化する
-
裁判所の審理が混乱する
通常は、
① 遺言無効訴訟
② 必要に応じて遺留分訴訟
と段階的に進める方が合理的です。
4 遺言無効でお悩みの方へ【仙台・宮城対応】
遺言無効の争いは、
-
感情対立が激しい
-
医療証拠の収集が重要
-
税務との連動が不可欠
という特徴があります。
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、
-
相続・遺言紛争の豊富な実績
-
税理士法人併設(東北地区で唯一の体制)
-
弁護士・税理士が直接対応
により、法務・税務を一体でサポートしております。
✔ 遺言が無効かどうか知りたい
✔ 認知症の遺言を争いたい
✔ 公正証書遺言でも無効になるのか相談したい
✔ 遺留分請求も同時に検討したい
という方は、お早めにご相談ください。
初回相談で、
-
見通し
-
必要な証拠
-
費用の目安
-
手続の流れ
を丁寧にご説明いたします。
無理な勧誘は一切ありません。
▼ 総合サイトはこちら
宮城・仙台で弁護士をお探しの方は”弁護士法人結の杜(ゆいのもり)総合法律事務所”へお任せください
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
『令和8年2月の土曜相談日』のお知らせ
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月2回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料】。
なお、令和7年12月より土曜相談日を月2回に変更させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
令和8年2月の相談日は次の通りです。
① 2月14日(土)(担当弁護士:三塚)
② 2月28日(土)(担当弁護士:髙橋)
お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。
相談場所は、原則として五橋本店となります。
(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)
また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。
皆様のご予約をお待ちしております。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
コラム「相続税対策|暦年課税制度と配偶者控除特例を活用した生前贈与の実務ポイント」
1 はじめに|「暦年贈与」と「配偶者控除」を正しく使えば相続税は大きく変わる
相続税対策として、生前贈与を検討される方は非常に多くいらっしゃいます。
なかでも代表的な制度が『暦年課税制度(年間110万円の基礎控除)』と、『贈与税の配偶者控除特例(最大2,000万円)』です。
もっとも、
-
贈与の方法を誤ると思わぬ贈与税・相続税が課税される
-
令和6年以降は生前贈与加算が「7年」に延長され、従来の感覚で対策すると失敗する
といった落とし穴も存在します。
本コラムでは、相続税を合法的に抑えるために知っておくべき暦年課税と配偶者控除特例のポイントを、法令・実務の両面から分かりやすく解説します。
2 暦年課税制度とは|毎年110万円まで非課税となる生前贈与
⑴ 暦年課税制度の基本
暦年課税制度とは、『1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額について、110万円まで非課税(基礎控除)』となる制度です。
この制度を活用し、毎年計画的に贈与を行うことで、
➡ 将来の相続財産を減らし
➡ 結果として相続税の負担を軽減
することが可能です。
⑵ 一般税率と特例税率(直系尊属からの贈与)
暦年贈与の税率には、以下の2種類があります。
-
一般贈与財産:配偶者・兄弟姉妹・子などからの贈与
-
特例贈与財産:直系尊属(父母・祖父母)から、18歳以上の子・孫への贈与
特例贈与財産に該当する場合は、税率が緩和された特例税率が適用されます。
⑶ 暦年贈与の税額計算方法(概要)
贈与税額は、次の計算式で求めます。
贈与税額 =(贈与額 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額
一般贈与財産と特例贈与財産が混在する場合は、法令に基づき按分計算を行う必要があります(措置法・通達)。
👉 税率表の正確な適用や有利不利の判断は専門的判断が不可欠です。
3 【重要】令和6年改正|生前贈与加算が「3年→7年」に延長
令和6年1月1日以後の贈与から、相続開始前7年以内の贈与が相続税に加算される制度に変更されました。
ただし、
-
延長された4年間分については合計100万円まで非加算
-
贈与の種類によっては加算対象外となる特例も存在
➡ 暦年贈与は「早め」「計画的」がこれまで以上に重要となっています。
4 配偶者控除特例|居住用不動産等の贈与は最大2,000万円まで非課税
⑴ 配偶者控除特例とは
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、
-
居住用不動産
-
居住用不動産を取得するための金銭
を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です(相続税法21条の6)。
⑵ 適用要件(チェックポイント)
以下すべてを満たす必要があります。
-
婚姻期間20年以上
-
国内の居住用不動産等であること
-
翌年3月15日までに居住・取得
-
過去に同一配偶者から配偶者控除の適用を受けていないこと
➡ 形式的要件を欠くと特例は適用不可となります。
⑶ 相続開始前7年以内でも「持ち戻し不要」
配偶者控除特例を適用した居住用不動産の贈与は、相続開始前7年以内であっても相続税に加算されません。
そのため、
-
相続税対策
-
配偶者の生活保障
の両面から、非常に有効な生前対策といえます。
5 相続開始年の贈与と「特定贈与財産」
相続開始年に行われた贈与は、原則として相続税の課税対象となります。
しかし、
-
婚姻期間20年以上
-
配偶者控除未使用
-
居住用不動産の贈与
という要件を満たす場合、「特定贈与財産」として生前贈与加算の対象外となります。
👉 相続税申告・贈与税申告の双方が必要となるため、専門家の関与が必須です。
6 遺産分割との関係|配偶者への贈与は「特別受益の持ち戻し免除」が推定
民法改正により、婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与・遺贈は、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。
➡ 相続人間の紛争予防という観点でも重要な制度です。
7 相続税対策は「法務×税務」の同時検討が不可欠
生前贈与や相続税対策は、
-
税務(贈与税・相続税)
-
民法(遺産分割・特別受益)
-
実務(名義・資金管理)
が複雑に絡み合います。
一部だけを見た対策は、後に大きなトラブルを招く可能性があります。
8 【結の杜総合法律事務所の強み】弁護士×税理士によるワンストップ相続対策
結の杜総合法律事務所では、税理士法人を併設し、弁護士・税理士である代表・髙橋が直接対応しております。
-
相続税対策
-
生前贈与の設計
-
遺産分割・遺留分対応
-
相続税申告
まで、一貫したワンストップ対応が可能です。
東北地区では数少ない体制で、実務に即したご提案を行っています。
9 まずは無料相談をご利用ください
制度を正しく使えば、相続税は大きく変わります。
一方で、誤った判断は税務否認・相続トラブルにつながります。
「この贈与は大丈夫?」
「今から何をすべき?」
とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
👉 初回相談無料・無理な勧誘は一切ありません
▶「お問い合わせ」はこちら
▶「結の杜総合法律事務所の総合サイト」はこちら
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
【重要なお知らせ】原香苗弁護士退職のお知らせ
平素より結の杜総合法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、当事務所所属の原 香苗弁護士は、令和7年12月31日をもって当事務所を退職いたしました。
また、従前お知らせいたしました通り、同日付をもって「泉中央支店」は閉業いたしました。
なお、税理士法人につきましては、本店(五橋)に併設された体制で引き続き業務を行っております。
法律相談・税務相談ともに、本店にてこれまでどおり対応可能ですので、ご安心ください。
今後の法律相談・ご依頼につきましては、五橋本店にて承ります。
引き続き、皆様の法的課題の解決に誠心誠意取り組んでまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
コラム「遺留分侵害額の算定方法とは? ― 生前贈与・遺言がある場合の具体的な計算と注意点を弁護士が解説 ―」
1 はじめに|「全財産を長男に」という遺言でも、何ももらえないとは限りません
相続において、次のようなご相談は非常に多く寄せられます。
Q
「夫が『全財産を長男に相続させる』という遺言を残して亡くなりました。
相続人である私や二男には、何か請求できる権利はあるのでしょうか。
また、遺留分侵害額はどのように算定するのですか。」
A
遺言によって相続分が指定されていても、一定の相続人には「遺留分」が保障されています。
遺留分侵害額は、
①相続開始時の財産+②一定期間内の生前贈与-③債務
によって算定され、その金額に法定相続分と遺留分割合を乗じて計算します。
本コラムでは、遺留分侵害額の具体的な算定方法について、条文・判例を踏まえながら、実務上問題となりやすいポイントを中心にわかりやすく解説します。
2 遺留分侵害額の基本的な計算式
遺留分を算定するための財産の価額は、次の式で計算します(民法1043条1項)。
遺留分算定の基礎財産
=
① 相続開始時に被相続人が有していた積極財産
+
② 遺留分算定の対象となる生前贈与
-
③ 被相続人の債務(借金・未払金など)
この金額に、
-
各相続人の法定相続分
-
各相続人の遺留分割合
を掛け合わせた額が、具体的な遺留分額となります。
相続や遺言によって取得した財産がこの金額に満たない場合、不足分について遺留分侵害額請求を行うことができます。
※遺留分侵害額の算定時点は相続開始時であり、相続開始後に誰かが債務を弁済していても、原則として算定に影響はありません(最判平成8年11月26日)。
3 「相続開始時に有していた財産」とは何か
ここでいう「財産」とは、被相続人の積極財産を指します。
(1)算入されるもの
-
不動産
-
預貯金
-
株式・投資信託
-
売掛金・貸付金 など
(2)算入されないもの
-
祭祀財産(仏壇・位牌・墓地等)(民法896条・897条)
(3)評価が難しい財産がある場合
条件付き権利や評価困難な権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価によって価格を定めます(民法1043条2項)。
4 生前贈与はどこまで遺留分算定に含まれるのか
生前贈与を自由に認めてしまうと、遺留分制度が形骸化します。一方で、すべてを遡及すると取引の安全が害されます。
そのため、民法は次のようなルールを定めています(民法1044条)。
(1)原則
-
相続開始前1年以内の贈与
→ 原則としてすべて算入 -
1年以上前の贈与
→ 贈与者・受贈者双方が「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合」のみ算入
(2)相続人への贈与の特則
相続人に対する贈与については、
相続開始前10年間にされた「特別受益」に該当する贈与が算入対象となります(民法1044条3項)。
(3)贈与と同視される行為
-
無償の信託利益の供与
-
共有持分の放棄
-
寄附行為 なども、贈与と同様に扱われます。
5 不相当な対価での売買(実質的な贈与)
時価とかけ離れた価格で行われた有償行為については、
当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合に限り、
贈与とみなされ、遺留分算定の対象となります(民法1045条2項)。
6 贈与の評価時点はいつか
-
相続開始前1年以内の贈与
→ 贈与契約時を基準(通説・裁判例) -
金銭贈与
→ 相続開始時の貨幣価値に換算して評価(最判昭和51年3月18日)
7 控除される「債務」の範囲
遺留分算定において控除される債務には、以下が含まれます。
(1)含まれるもの
-
借金・未払金
-
租税・公租公課
-
罰金などの公法上の債務
(2)含まれないもの
-
相続税
-
遺産管理費用
-
遺言書検認申立費用 など
相続人自身が被相続人に対して有していた債権・債務についても、混同による消滅を前提とせず、相続開始時の客観的財産状態を基準に判断されます(さいたま地裁平成21年5月15日判決)。
8 「全財産を一人に相続させる」遺言がある場合の算定
相続人の一人に全財産を相続させる遺言がある場合でも、他の相続人は遺留分侵害額請求を行うことができます。
この点につき、最高裁平成21年3月24日判決は、
相続債務も含めて指定相続人が承継するのが原則としたうえで、
遺留分侵害額の算定において、
遺留分権利者の法定相続分に相当する債務額を加算することはできない
と明確に判断しています。
9 「遺留分権利者に損害を加えることを知っていた」とは?
贈与当事者に悪意や害意まで必要ではありませんが、
-
贈与財産が残存財産を上回ること
-
将来、財産状況に大きな変動がないこと
などを具体的に認識していたことが必要とされています(大判昭和11年6月17日)。
10 まとめ|遺留分侵害額の算定は専門的判断が不可欠です
遺留分侵害額の算定は、
-
生前贈与の有無・時期
-
不動産や株式の評価
-
債務の取扱い
-
遺言の内容
など、高度な法的判断と実務経験が不可欠です。
少しの評価の違いで、請求できる金額が大きく変わることも珍しくありません。
11 弁護士への相談のご案内
結の杜総合法律事務所では、
-
遺留分侵害額請求が可能かどうか
-
おおよその請求額の見通し
-
手続の流れ・期間・費用
について、弁護士が直接、丁寧にご説明しております。
無理な勧誘は一切ありません。
まずはお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
『令和8年1月の土曜相談日』のお知らせ
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、原則として毎月2回、土曜日も法律相談を受け付けております(完全予約制)。土曜相談をご希望の方は、直近の営業日までに、お電話またはお問い合わせフォームからお申し込みください【新規のお客様は初回1時間無料】。
なお、令和7年12月より土曜相談日を月2回に変更させていただきます。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
令和8年1月の相談日は次の通りです。
① 1月17日(土)(担当弁護士:髙橋)
② 1月31日(土)(担当弁護士:三塚)
お時間については、ご予約時にご希望をお伺いして決めさせていただきます。
相談場所は、原則として五橋本店となります。
(なお、ご予約状況によってはご希望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。)
また、当事務所では、直接面談形式の法律相談に加え、「zoom」アプリを利用したテレビ電話形式での法律相談も行っております。こちらもぜひご活用ください(詳しくはこちら)。
皆様のご予約をお待ちしております。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
【重要なお知らせ】泉中央支店閉業のお知らせ(令和7年12月末)
このたび、当事務所では事業再編および業務効率化の一環として、
「泉中央支店」を令和7年(2025年)12月末日をもって閉業することとなりました。
これまで泉中央支店をご利用いただいた皆様には、心より御礼申し上げます。
閉業後の業務につきましては、仙台五橋本店および東京支店にて引き続きご相談・ご依頼を承りますので、ご安心ください。
■ 閉業日
令和7年12月31日(予定)
■ 閉業後の対応について
- 現在ご依頼中の案件は、担当弁護士がそのまま職務を遂行いたします。
- 新規のご相談・ご依頼は、仙台五橋本店、東京支店にて通常どおり受け付けております。
- これまで泉中央支店をご利用いただいていた方も、支店閉業後は全ての窓口でご相談いただけます。
弁護士法人結の杜総合法律事務所
(仙台五橋本店)
〒980-0022 仙台市青葉区五橋一丁目1番17号 仙台ビルディング駅前館9階
TEL:022-797-0741
FAX:022-797-0641
皆様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、職員一丸となって職務を遂行して参りますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
年末年始休業のお知らせ
誠に勝手ながら、弁護士法人結の杜総合法律事務所は、以下の日程を年末年始休業とさせて頂きます。
【年末年始休業期間】 12月27日(土)~1月4日(日)
【業務開始日】 1月5日(月) ~平常どおり、営業致します。
休業期間中のFAX、E-Mail、ホームページ専用フォームによるお問い合わせは受け付けておりますが、お問い合わせに対する回答は、1月5日(月) 以降になりますのでご了承くださいませ。 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
コラム「遺言執行者とはどのようなことをするの?|選任が必要なケースと手続を徹底解説」
1 はじめに
「遺言書があるのに遺言執行者の指定がない。相続人は遺言執行者を選任しなければならないのか?」
「家庭裁判所で遺言執行者を選任する場合、どんな手続や書類が必要なのか?」
遺言・相続のご相談では、このような質問を多く頂きます。
この記事では、遺言執行者が必要となるケース、選任手続、就任後の具体的な業務内容まで専門家が分かりやすく解説します。
2 遺言執行者はいつ必要?|選任の要否を分かりやすく解説
遺言書の内容は大きく次の3つに分かれ、内容によって「遺言執行者が必須かどうか」が異なります。
① 遺言執行者だけが執行できる事項(必ず選任が必要)
-
推定相続人の廃除(民893)
-
推定相続人の廃除の取消し(民894②)
-
認知(民781②)
これらは遺言執行者がいなければ法的に効力を実現できない内容のため、遺言執行者の選任が不可欠です。
② 遺言執行者・相続人どちらでも執行できる事項(トラブル防止のため選任が望ましい)
-
遺贈(民964)
-
一般財団法人の設立(一般法人152②)
-
信託の設定(信託3二)
-
生命保険金受取人の変更
相続人間で意見が分かれたり、協力を得にくい場合は、遺言執行者を選任することで手続がスムーズになり、争いの予防につながります。
③ 遺言執行が不要な事項(選任不要)
-
相続分の指定(民902)
-
遺産分割方法の指定(民908)
-
遺産分割の禁止(民908)
-
遺言執行者の指定(民1006①)
-
遺言の撤回 など
上記のように、内容により遺言執行者の必要性は異なります。
遺言の種類・構成を正しく判定することが重要であり、専門家に確認するメリットの大きいポイントです。
3 遺言執行者を家庭裁判所で選任する手続|必要書類・期間の目安
遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が就任できない事情がある場合には、家庭裁判所で選任手続を行います(民1010)。
■ 選任申立てができる人(利害関係人)
-
相続人
-
受遺者
-
遺言者の債権者
-
相続財産管理人
-
相続財産清算人 など
■ 管轄の家庭裁判所
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所(家事209①)。
■ 必要書類(標準的なもの)
-
被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)
-
遺言書(写しまたは検認調書謄本)
-
遺言執行者候補者の住民票等
-
利害関係を証する資料(戸籍等)
※遺言書が検認済の場合、家庭裁判所に記録が残っていれば一部省略が可能。
■ どんな場合に裁判所は選任する?
-
遺言内容に「遺言執行者必須事項」が含まれる
-
相続人間の対立があり、遺言の内容が実現できない
-
相続人の協力が得られない
-
相続財産が多岐にわたり管理が複雑
遺贈が絡む案件や相続人が複数いるケースでは、家庭裁判所での選任は非常に一般的です。
4 遺言執行者の具体的な業務内容(時系列で理解)
遺言執行者は、遺言内容を実現するために幅広い権限と義務を持ちます(民1012)。
(1)遺言書の検認手続(必要な場合)
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で「検認」を行います(民1004)。
検認前に開封してしまうと過料の対象となるため注意が必要です。
※公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は検認不要。
(2)遺言書の正本・謄本の取得(公正証書遺言の場合)
相続手続で必要となるため、公証役場で請求して取得します。
(3)遺言書情報証明書の取得(自筆証書遺言・法務局保管)
(4)遺言の有効性の確認(方式・遺言能力・内容)
方式違背や遺言能力の欠如が疑われる場合、無効確認訴訟が検討されます。
(5)相続人・受遺者の調査・通知(民1007)
出生から死亡までの戸籍を取り寄せて相続人を確定し、遺言内容を通知します。
受遺者に対しては遺贈の受諾の意思確認も必要です。
(6)財産目録の作成・交付(民1011)
不動産・預貯金・株式・保険等を調査し、相続財産を目録にまとめ相続人へ交付。
(7)遺言の実現(執行)
-
不動産の名義変更
-
銀行口座の払い戻し
-
遺贈財産の引渡し
-
廃除手続 等
遺言執行者は「善良な管理者の注意義務」を負いながら業務を行います。
(8)遺言執行終了の通知
執行が完了したら相続人等に終了を通知します(民1020)。
(9)報酬・費用の精算
遺言に記載がある場合はその通り。
ない場合は相続人との協議、合意できなければ家庭裁判所が決定します。
5 まとめ|遺言執行者の選任は専門家に相談することで安心・確実に進められます
遺言執行者は、
-
遺言書の確認
-
相続人の調査
-
名義変更
-
遺贈手続
-
財産管理
など、法律知識と実務経験が必要な場面が多く、専門性の高い業務です。
特に、
-
相続人間の対立がある
-
不動産・預貯金・株式等の財産が複雑
-
遺贈がある
-
廃除や認知など法律行為を含む
といったケースでは、専門家が遺言執行者になることでスムーズに手続が進みます。
6 当事務所が選ばれる理由|弁護士×税理士によるワンストップ相続サービス
弁護士法人結の杜総合法律事務所では、
弁護士・税理士である代表髙橋が、法律と相続税の両面からサポートいたします。
-
相続・遺言・遺産分割に強い弁護士が対応
-
税理士法人を併設(東北地方で唯一の運営形態)
-
相続税申告までワンストップ対応
-
事前に費用・手続の流れを丁寧に説明
-
強引な勧誘なし・安心して相談できる体制
遺言執行だけでなく、遺産分割・相続税申告・財産調査まで一括対応が可能です。
まずはお気軽にご相談ください。
宮城県仙台市にある弁護士法人結の杜総合法律事務所は、弁護士と税理士が連携し、遺言・相続に関する無料相談を提供しています。当事務所では、相続トラブルや手続きの悩みに対し、専門チームが丁寧に対応いたします。初回相談や費用見積もりは無料で、仙台・宮城の皆様に寄り添ったサービスを心掛けています。相続に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。